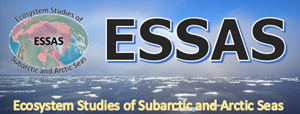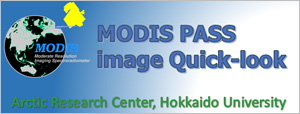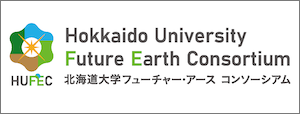センター長挨拶
 北極域研究センター長
北極域研究センター長
深町 康2015年4月に設立された当時、齊藤前センター長1 名の体制であった本センターですが、現在では専任教員8名、学内関係部局の兼務教員33 名の体制となり、異分野連携・融合研究、産官学連携などのミッションに取り組んできました。代表的な例としては、本センターを中心とした本学は、2015 年9 月に開始された我が国の北極域研究の国家プロジェクトである北極域研究推進(ArCS)プロジェクト(文部科学省補助金事業)に副代表機関(代表機関は国立極地研究所、もう一つの副代表機関は国立研究開発法人海洋研究開発機構)として参画しました。さらにその後継の北極域研究加速(ArCS II)プロジェクトが2020年6月に開始され、本学は引き続き副代表機関として企画運営に携わるとともに、沿岸環境課題「北極域における沿岸環境の変化とその社会影響」、国際政治課題「複雑化する北極域政治の総合的解明と日本の北極政策への貢献」などの国際共同研究及び若手研究者海外派遣事業を実施しています。
2016年4月には、北極域における環境と人間の相互作用の解明に向けた異分野連携による課題解決に資する研究の進展を図るため、北極域研究共同推進拠点として文部科学省の共同利用・共同研究拠点に認定されました。本拠点は本センターを中核施設、国立極地研究所・国際北極環境研究センターと国立研究開発法人海洋研究開発機構・北極環境変動総合研究センターを連携施設とした初めての連携ネットワーク型の体制となっており、公募研究による研究者コミュニティの支援、セミナーの実施や公募研究による産官学連携の推進、北極課題の解決のための人材育成を行ないました。さらに2020年4月には、「世界を牽引する課題解決型の北極域研究拠点の構築(HAI-FES : Hokkaido University Arctic Initiatives for Future Earth and SDGs)」プロジェクトを開始し、本学の北極域研究者が部局を超えて結集し、拠点を構築するとともに、国際協働研究プラットフォームであるフューチャーアースのもとで北極域ネットワークを構築し、課題解決型の北極研究を実施することを目指した活動を続けています。
今後も、北極域の持続可能な開発・利用・保全の推進に寄与するというビジョンに基づいて、本センターおよび共同利用・共同研究拠点の活動を通して、その役割を果たしていく所存です。皆様のより一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
2023年8月 深町 康